久しぶりのラテンベース入門の更新です。
色々とトピックはあるなと思いつつも、どこからとりあげるべきかと順番が難しく思っているのですがまずは思いつく順に各リズムについて更新していこうと思っています。
今回はSon(ソン)について書いていこうと思います。
Son(ソン)とは
Son(ソン)はキューバのオリエンテ州で生まれました。
スペイン音楽とキューバ音楽それぞれの文化の影響を組み合わせできた音楽です。
もっともキューバ的な音楽でサルサの原型となった音楽と言われています。
そして、Danzon(ダンソン)がCha-Cha-Cha(チャチャチャ)やMambo(マンボ)に発展していくのに影響も与えています。
ということで、様々なキューバ音楽において大きな存在となる音楽です。
ルンバって言われがち
Son(ソン)はキューバばかりでなく、世界的に知られる音楽となりました。
「El Manisero(南京豆売り)」という曲が、世界的に大ヒットしました。
これがアメリカへ持ち込まれた際に「Son(ソン)という言葉が英語のSongと混同されるから…」という理由でRhumba(ルンバ)と表記されることになってしまいました。
社交ダンスなどでもRhumba(ルンバ)という名前で組み入れられてしましました。
本来のキューバ音楽におけるRumbaと混乱してしまいがちですよね。
そこから大きく誤解と勘違いがうまれ、今もなお混乱が続いているわけです。
表記も現在ではどちらもRumbaとされているので単語を見ても見分けはできません。
ラテン音楽以外の人から 「ルンバで!」と言われた時は要注意です。
Son(ソン)に使われる楽器の変遷
もっとも初期のSon(ソン)では、ベースパートにはBotija(ボティーハ)という素焼きの壺、もしくはMarimbula(マリンブラ)という親指ピアノを使っていました。
ここで使われている壺がBotija(ボティーハ)です。
Marimbula(マリンブラ)
最も初期の編成ではギター、トレス、Botija(ボティーハ)もしくはMarimbula(マリンブラ)というものでした。
そしてこれにBongo(ボンゴ)が加わり、Guiro(ギロ)が加わり。
ベースパートはウッドベースが使われるようになっていきました。
これがSextet(セステート/六重奏団)編成となっていきます。
グループによって多少の差はありますが、基本的にはギター、トレス、ベース、ボンゴ、ギロ、マラカス、クラベスといった編成です。
さらに1927年には、トランペットが加わりSepteto(セプテート/七重奏団)以降のSon(ソン)における基本的な編成として定着していきます。
楽曲の構成としてはメロディのいわゆる歌曲のテーマ部分(これをギアと称します。)があり、その後に後半にCoro-Canta(コロカンタ)を行うMontuno(モントゥーノ)セクションという構成になっています。
代表的なSon(ソン)の曲
有名な代表曲といえるようなものをいくつか紹介してみます。
“Echale Salsita”
“Son de la Loma”
“El Cuarto de Tula”
“Lagrimas Negras”(Bolero-Son)
https://youtu.be/tozhe0yTAqo
他にもたくさんの名曲がありますがひとまずこんなところで。
以下はSpotifyにて、代表的と言えるSonのアルバムを紹介します。
これらも是非聴いてみてSon(ソン)の理解を深めて下さい。
Son(ソン)のベースライン
ようやくSon(ソン)のベースラインについてです。
Tumbao(トゥンバオ)のパターンは下記のようなものが多いです。

2分音符と4分音符でできたベースラインです。

Ex.1の3拍目をシンコペーションさせてリズミックにしたものです。

Ex.2を更に変化させ4拍目を次の小節にシンコペーションさせたものです。
サルサなどでもよくあるトゥンバオのパターンですね。

"Echale Salsita"イントロ部分のベースラインです。
Ex.1と同様のベースラインとなります。

"Son de la Loma"のテーマに入った冒頭部分のベースラインです。
Ex.2と同様のベースラインとなります。
モントゥーノでのよくあるベースライン

Ⅰ-Ⅳ-Ⅴ7での典型的なベースラインになります。

Ex.6をリズミックにしたものです。
ということで、Son(ソン)について簡単に説明してきました。
他のキューバ音楽やサルサのルーツと言えるものですし、今もなおSon(ソン)の名曲たちは様々なところで歌われています。
是非とも色々研究してみて下さい。
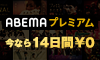








「ラテンベース入門 「Son(ソン)のベース」」への2件のフィードバック